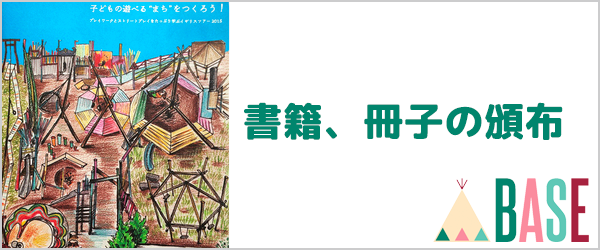事業概要
とうきょうご近所みちあそびプロジェクト

とうきょうご近所みちあそびプロジェクトは「大人も子どもも住みよいまち」をつくることを目的に、身近な道や公共空間を利用してご近所に一時的な交流の場をつくる取り組みです。
多世代交流や子育て支援、孤立の解消、商店街振興や防犯、防災など、さまざまな分野で効果が期待されます。
TOKYO PLAYでは、実施する市民や事業として取り組む自治体のサポートを行っています。



渋谷どこでも運動場プロジェクト

渋谷区では、基本構想に「思わず身体を動かしたくなるまち」を掲げ、区全体を「15㎢の運動場」と捉え、日常的な運動も、楽しみで行うスポーツも、すべてが暮らしに溶け込むようなまちづくりを進めています。
渋谷どこでも運動場プロジェクトは、くらしに身近な道路や緑道、公園など、人が行き交う場所を使って、スポーツや遊びを通して体を動かしながら、地域に住んでいる人同士がつながることのできる機会づくりに取り組む個人・団体を応援する事業です。
TOKYO PLAYが渋谷区より委託をうけ、渋谷の遊び場を考える会の協力のもと運営しています。



インクルーシブな遊び場づくり
誰でも利用できるはずの遊び場や公園。ですが、障がいの有無や年齢、言葉が通じないなど見えない壁を感じて利用しにくい子どもたちがいます。TOKYO PLAYでは、遊びを通して地域にインクルーシブな環境がつくられていくプロセスのお手伝いをしています。
砧公園「みんなのひろば」利用・理解促進
都立砧公園に整備された遊具ひろば「みんなのひろば」は、地域に根ざしたインクルーシブな社会づくりの発信地を目指しています。都立公園を管理する(公財)東京都公園協会と協働し、利用および理解促進に向けてプロジェクトを進めています。



とうきょうプレイデー

毎年10月1日都民の日を「とうきょうプレイデー」、その前後の期間を「プレイデーWEEK」として定め、遊ぶことの大切さをみんなで感じ、考えるキャンペーンです。一緒にキャンペーンを盛り上げる仲間やスポンサーも募集しています。
国際遊びの日

2024年3月の国連総会において、遊ぶことの大切さを国際的に啓発する「国際遊びの日(International Day of Play)」が制定されました。毎年6月11日に、世界各地でこの日を祝い、様々な普及啓発活動が行われています。
TOKYO PLAYは、2024年より、オンラインセミナーなどを通じて国際遊びの日に関する活動を行っています。一緒にキャンペーンを盛り上げてくださる仲間やスポンサーも募集しています。
子どもの声を聴く
2023年4月に施行されたこども基本法では、こどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念として掲げられ、こども施策の策定等に当たって「こどもの意見の反映に係る措置を講ずること(第11条)」が国や地方公共団体に対し義務付けられました。
TOKYO PLAYでは、子ども自身が安心して自分の思いを表現することができるよう、かたちだけではない子どもの声を聴く取り組みを進めています。
子どもと対話するファシリテーターには、日常的に子どもと対話する業務に従事した経験を重要視し選ばれたスタッフが、独自の研修を受け、携わっています。
これまでの実績
- 子供の居場所におけるヒアリングに係る業務(東京都)/2024年度
- せたがや子ども気候会議における運営補助業務(世田谷区)/2023年度
- 子供へのヒアリング実施及び分析に関する業務委託(東京都)/2023年度
- 次世代育成支援東京都行動計画(後期)の評価に係る調査報告書(東京都)/2011年度
子ども計画策定・権利条例策定
これまでの専門的な知識やノウハウを活かし、子どもの声を反映した子ども計画や子どもの遊びに関する指針づくりのお手伝いをします。
これまでの実績
- 子ども青少年会議(世田谷区)/2024年度
- (仮称)子ども条例策定支援業務(狛江市)/2024年度〜
- (仮称)子ども条例検討ワークショップ運営(狛江市)/2025年度
人材育成・講師派遣
子どもが遊ぶことの大切さや、遊びに関わる大人の役割について学びたい方たちを応援します。一般向けの入門的な内容から、お仕事で携わる方たちに向けた専門研修や長期伴走型の支援まで幅広く対応します。
シンポジウムやフォーラム等の登壇もご相談ください。
主催講座
子どもが遊ぶことの大切さや、遊びに関わる大人の役割、子どもが豊かに遊べる環境づくりや遊びにまつわる海外の先進事例について関心のある方に向けて、様々な講座やスタディツアーを企画しています。
※登壇者などの順番は、基本五十音順。肩書きは開催時のもの。
国際遊びの日 オンラインランチセミナー(2025年度)
【登壇】
内山 悠 さん(IPA日本支部 運営委員)
寺田 光成 さん(日本体育大学 体育学部 助教)
渡邉 祐士 さん(世田谷区 子ども・若者部副参事(児童施策推進担当)児童課長兼務)
【進行】
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
シリーズ「はじめの100か月の育ちビジョン」をどう読み解くか(2024〜2025年度)
第1回 ビジョンに書かれている社会的まなざしとは
【登壇】
岩﨑 貴行 さん(こども家庭庁 成育局 成育基盤企画課 主査)
大豆生田 啓友 さん(玉川大学教育学部 教授)
山口 有紗 さん(小児科医|児童精神科医)
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
【ファシリテーター】
土肥 潤也 さん(NPO法人わかもののまち 代表理事|C&Yパートナーズ 代表取締役)
【制作協力】
株式会社ディレクションズ
第2回 ビジョンの実現に向けて 課題の抽出と解決アプローチの検討
【進行】
土肥 潤也 さん(NPO法人わかもののまち 代表理事|C&Yパートナーズ 代表取締役)
【話題提供】
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
【グラフィックレコーダー】
石橋 智晴 さん(横浜創英中学・高等学校)
【制作協力】
株式会社ディレクションズ
第3回 実践大公開!ウェルビーイングな地域づくり
【登壇】
井内 聖 さん(安平町教育長)
仲 綾子 さん(東洋大学福祉社会デザイン学部人間環境デザイン学科 教授)
紅谷 浩之 さん(医療法人オレンジグループ 代表)
土肥 潤也 さん(NPO法人わかもののまち 代表理事|C&Yパートナーズ 代表取締役)
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
【グラフィックレコーダー】
石橋 智晴 さん(横浜創英中学・高等学校)
【制作協力】
株式会社ディレクションズ
第4回 総集編!みんなで考える
【登壇者】
安宅 研太郎 さん(建築家|パトラック 代表取締役)
岩﨑 貴行 さん(こども家庭庁 成育基盤企画課 指針係主査)
大豆生田 啓友 さん(玉川大学教育学部 教授)
長田 浩志 さん(元こども家庭庁設立準備室 審議官)
土肥 潤也 さん(NPO法人わかもののまち 代表理事|C&Yパートナーズ 代表取締役)
松田 妙子 さん(NPO法人せたがや子育てネット 代表理事)
山口 有紗 さん(小児科医|児童精神科医)
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
【ファシリテーター】
青木 将幸 さん(青木将幸ファシリテーター事務所)
【グラフィックレコーダー】
石橋 智晴 さん(横浜創英中学・高等学校)
【協力】
サイボウズ株式会社
ソレアドカフェ(カフェ出店)
【制作協力】
株式会社ディレクションズ
映画「ゆめパのじかん」は世界の目にどう映ったのか?
ー海外初上映ツアーから考える「子どもの居場所の現在地」(2024年度)
【登壇者】
重江 良樹 さん(映画「ゆめパのじかん」監督|映像制作・企画「ガーラフィルム」代表)
西野 博之 さん(認定NPO法人たまりば 理事長|川崎市子ども夢パーク 前所長)
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
【協力】
サイボウズ株式会社
国際遊びの日 ランチセミナー(2024年度)
【登壇者】
内山 悠 さん(IPA日本支部 運営委員)
関戸 博樹 さん(NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表)
山田 心健 さん(セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
シリーズ「環境問題として考える子どもの遊び」学習会(2018〜2019年度)
第1回 私たちはどう動く? 『子どもは外で遊ばない』が当たり前になるその前に
【講師】
神林 俊一 さん(プレーワーカーズ 事務局長)
寺田 光成 さん(千葉大学木下研究室)
第2回 人がつながる場所の作り方 〜制度やサービスの限界を超えるために必要なこと〜
【講師】
西川 正 さん(NPO法人ハンズオン埼玉 代表理事)
松田 妙子 さん(NPO法人せたがや子育てネット 代表理事)
第3回 子どもの身体がおかしい⁉︎ 光・暗闇・外遊び〜ワクワクドキドキのススメ〜
【講師】
野井 真吾 さん(日本体育大学 教授)
第4回 子どもの遊びのこれまでとこれから IT社会の終わり!?に可能性しか感じない光・暗闇・外遊び〜ワクワクドキドキのススメ〜
【講師】
犬飼 博士 さん(遊物体アソビウム)
番外編 これまでのふりかえり 社会を変える私たちは、今後何を学ぶべきか
【ファシリテーター】
嶋村 仁志(TOKYO PLAY 代表理事)
海外の実践団体との連携
イギリス ー London Play
1998年に設立した法人です。「We work for a more playful London / もっと遊びあふれるロンドンをめざして」をビジョンに掲げ、ロビー活動や調査研究、コンサルティング、キャンペーンなどの手法で、行政と市民、実践者、NPO、研究者、企業をつなぎ、子どもの遊び環境づくりに取り組んでいます。プレイストリート(ご近所みちあそび)やプレイデーの実践は、London Playの取り組みを参考にしている部分も大きく、TOKYO PLAYが実施しているスタディツアーの現地パートナーでもあります。

ロンドンー東京 遊びの姉妹都市提携
2016年2月、TOKYO PLAYとLondon Playは正式に姉妹団体となり、遊びに関する人と情報の交流を盛んにするため、「Twin Play Cities」として「ロンドン-東京 遊びの姉妹都市提携」を結びました。
イギリススタディーツアー(2014、2015、2016、2019年度)
世界有数の大都市、東京が発信する子どもの遊びに関わる方針や施策は、世界からも注目を集めています。
TOKYO PLAYは、IPA(International Play Association)での活動を通じた海外とのネットワークを活かし、海外の「子どもの豊かな遊びの環境づくり」に取り組む団体と連携し、情報交換・協働事業を進めています。



香港 ー Playright 智楽児童遊楽協会
「子どもたちが子ども時代を楽しむことができる子どもの遊ぶ権利を尊重し、保護し、実現する社会の構築」を目指し、1987年に設立した法人です。室内外の遊び環境づくりはもちろん、親子へのアウトリーチ、調査研究、資格制度やアカデミーの設立まで幅広く活動しています。TOKYO PLAYは、2014年から始まったプロジェクト「Community Build Playground(移動式遊び場)」「1/2 Playground(子どもと大人がともに育てる遊び場)」の公式アドバイザーとして、香港での実践指導や日本での視察の受け入れを行っています。
ベトナム ー Think Playgrounds
2014年に設立し、ベトナム国内の様々な条件下で100を超える遊び場、コミュニティスペースをつくってきた子どもの遊びを支える団体です。2019年、国際交流基金の助成金を受け、首都ハノイで国内初の冒険遊び場の開設プロジェクトが始動し、TOKYO PLAYは、日本での視察受け入れ、現地での講演・研修・候補地の開拓・実践指導を担いました。ベトナムでのプレイワーク普及に向け、今後も共同で事業を展開していきます。
台湾 ー 実践団体とのつながり
PPfCC – Parks Playgrounds for Children by Children 還我特色公園行動同盟(台湾)
子どもの遊び環境の改善に取り組むため2015年に設立した法人です。台湾のテレビ局による「みちあそび」特集取材を通してつながり、みちあそびやインクルーシブな遊び場についての情報交換を行っています。
子どもの遊びと大人の役割 研究所
「『遊ぶ』の力をすべての子どもに」を掲げるTOKYO PLAYが、これまでに様々なプロジェクトを通して蓄積した知見や情報を整理すると共に、新たな調査や研究、プロジェクトや学習会の実施に取り組み、子どもの遊びにやさしい社会の実現に貢献していきます。
TOKYO PLAYがこれまでに関わったプロジェクトや調査研究の資料をダウンロードすることができます。
これまでの主な執筆
・『こわかけんマガジン』(子ども・若者参画研究会)
2025年7月:実践報告
東京都 こども意見聴取の実践報告 大野 さゆり
・『月刊チャイルドヘルス』(診断と治療社)
2024年5月:特集「子どものウェルビーイングをはぐくむ環境」
あそびと子ども 嶋村 仁志
・学術誌『Children, Youth and Environments』第28巻第2号58-66ページ(University of Cincinnati)
2018年「Street Play in the Revitalization of Low-Birthrate Communities: Playborhood Street Tokyo」
著:嶋村 仁志/doi:10.7721/chilyoutenvi.28.2.0058.
・『新都市』(公益財団法人都市計画協会)
2016年12月:特集「子育てしやすいまちづくり」
「みち」から育てる子育てしやすいまちづくり 嶋村 仁志
・『こども環境学会研究』Vol.12, No.3 (公益社団法人こども環境学会)
2016年12月:「特集:外遊びのいま」
(巻頭対談)嶋村 仁志×野井 真吾 「特集:外遊びのいま」
これまでの主なメディア掲載情報
・『東京新聞』
2025年5月5日:「子どもの意見 すくえていますか?」
・『フィランソロピー』(公社日本フィランソロピー協会)
2023年8月:「『遊ぶ』ことは、自分の人生の『今』を自分で決めること」
・『Yahoo!JAPAN SDGs』
2023年3月:「いま増えているインクルーシブ公園ってなに?」
・『クーヨン』(クレヨンハウス)
2023年3月:「広がる!インクルーシブ公園」
・『毎日新聞』
2022年11月:「車いすで砂遊び、遊具に背もたれ『インクルーシブ公園』広がる」